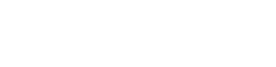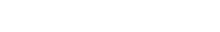About
三浦小平二について




三浦小平二の歩み
History
- 1933年
-
新潟県佐渡市相川、 無名異焼(むみょういやき)窯元小平窯、
三浦小平の長男として生まれる。
祖父は三代 三浦常山。
初代常山は 幕末硬質な無名異焼をつくり焼き物を産業化させた人として
佐渡相川のやきもの史に位置付けられている。
- 1951年
-
東京藝術大学彫刻科(平櫛教室)に入学。
高田直彦氏と共に陶磁器研究会をつくり 芸大初の窯を築く。
加藤士師萌に師事。
- 1955年
-
東京藝術大学を卒業。
京都製陶会社に就職。 職人的な修練を積む。
その後 岐阜の陶磁器試験場 研究生となり釉薬等を研鑚。
- 1958年
-
東京藝術大学の陶磁器研究室の副主となる。
- 1960年
-
国立市のママの森幼稚園 美術講師となる。
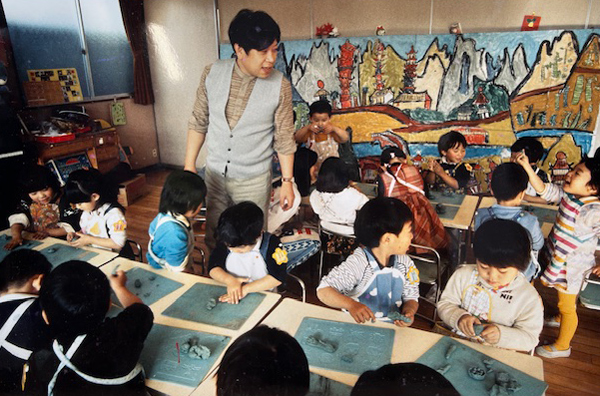
- 1961年
-
ママの森幼稚園 園長の五味竹子と結婚。
- 1972年
-
台湾 故宮博物院にて青磁、赤絵を学ぶ。
- 1973年
-
父 小平の死により 佐渡小平窯を継ぐ。
- 1986年
-
日本工芸会 理事に就任。
- 1987年
-
西新宿にて交通事故にあう。
- 1990年
-
東京藝術大学工芸科陶芸講座 教授に就任。
- 1992年
-
佐渡市相川町(生家)に 『 三浦小平二 小さな美術館』 を設立。
- 1996年
-
紫綬褒章 受賞。

- 1997年
-
重要無形文化財 青磁で初の 人間国宝 に認定される。
- 2000年
-
東京藝術大学 名誉教授 に就任。
文星芸術大学 教授 に就任。
- 2004年
-
三浦小平二意匠 『佐渡物語』 として商標登録。
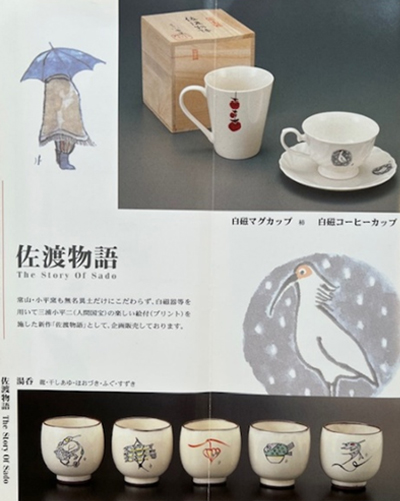
- 2005年
-
文星芸術大学 客員教授となる。
- 2006年
-
作陶50周年展 終了後 10月3日国立市の自宅にて逝去(73歳)。
- 2010年
-
佐渡市 名誉市民となる。
- 2014年
-
『Koheiji Miura』と命名された 星 が誕生。
(天文家 佐藤真人氏 発見の小惑星)
- 2021年
-
三浦竹子 記念館のオープンを目指し
一般財団法人 Musée Miura を設立。

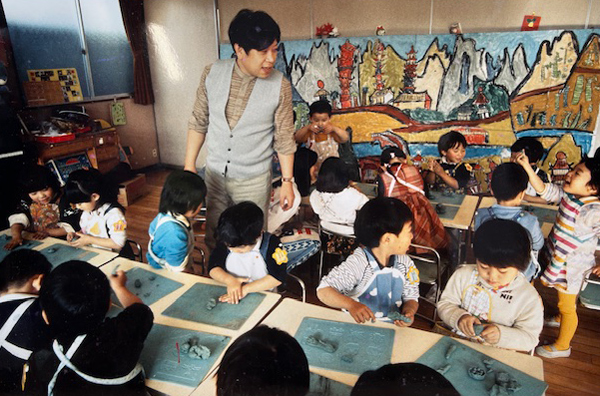

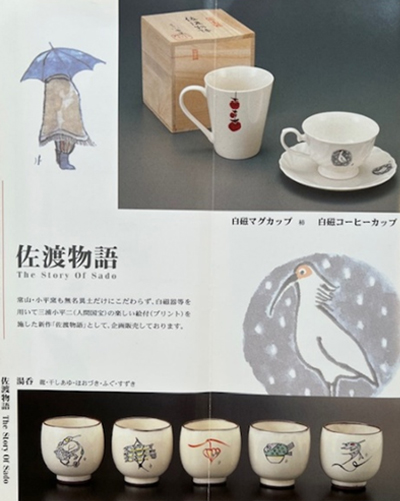

三浦小平二 陶歴
History
- 1961年(28歳)
-
第4回 新日展 入選
- 1962年(29歳)
-
第10回 現代日本陶芸展 朝日新聞社賞受賞
- 1967年(34歳)
-
第7回 伝統工芸新作展 優秀賞受賞(釣窯花瓶)
- 1968年(35歳)
-
第1回個展 日本橋三越
- 1970年(36歳)
-
第2回個展 テーマ「マサイ」日本橋三越
- 1976年(43歳)
-
第5回個展 テーマ「青磁」日本橋三越
第23回 日本伝統工芸展文部大臣賞受賞(青磁大鉢)文化庁買上
- 1977年(44歳)
-
昭和51年度 日本陶芸協会賞受賞
個展 大阪高島屋
- 1978年(45歳)
-
第6回個展 テーマ「アフガニスタン」日本橋三越
新潟日報主催 「三浦常山、小平、小平二展」 大和新潟店
新潟県立近代美術館、敦井美術館 買上
- 1979年(46歳)
-
個展 大阪高島屋
- 1980年(47歳)
-
第7回個展 テーマ「モンゴル 中国」日本橋三越
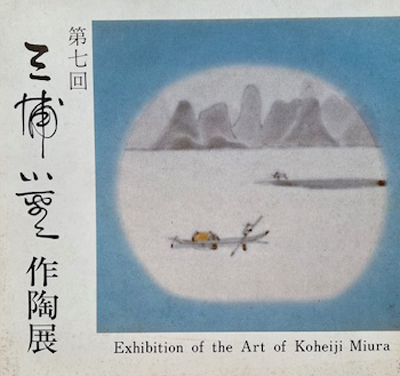
- 1981年(48歳)
-
『 堀柳女 三浦小平二 形色展 』 名古屋松坂屋
毎日新聞主催 『 日本陶芸展 』推薦招待出品 以降隔年出品
- 1982年(49歳)
-
第8回個展 テーマ「長江と西域の風物」
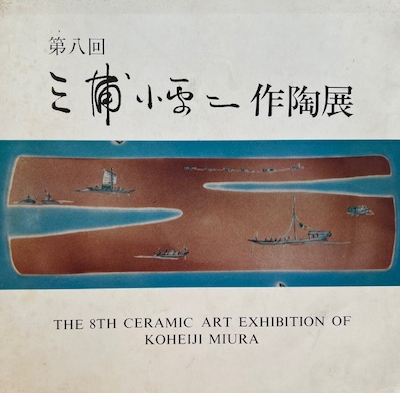
- 1983年(50歳)
-
国際交流基金主催 『 カナダ巡回日本陶芸展 』 招待出品
現 日本陶芸(菊池コレクション) 招待出品
スミソニアン協会自然史博物館(ワシントン) 招待出品
ビィクトリア&アルバート美術館(ロンドン) 招待出品
『 三浦小平二 作陶展 』 大阪高島屋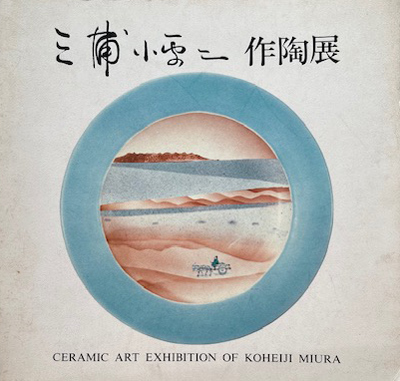
- 1984年(51歳)
-
日本のやきもの「皿と鉢100選」 サントリー美術館 招待出品
個展 西武高輪会
- 1985年(52歳)
-
浩宮殿下留学記念として青磁花瓶 エリザベス女王陛下に贈られる。
日本のやきもの「色絵100選」 サントリー美術館 招待出品
第32回 『日本伝統工芸展』 鑑査委員 (34回 36回 39回 43回)
第9回個展 「 佛への道 インドから日本 」 日本橋三越
- 1986年(53歳)
-
《 青磁飾り壺 ロバ 》 ヴィクトリア&アルバート美術館買上
《 青磁豆彩大皿 曼荼羅文 》 東京国立近代美術館買上
日本工芸会理事に就任
- 1987年(54歳)
-
《 青磁飾り壺 佛手 》
《 青磁大皿 曼荼羅 》 国際交流基金買上
- 1990年(57歳)
-
「 三浦小平二青磁展 」 パリ ニューヨーク ギャラリーアーバン
「 青磁 過去―現代の源泉 」をテーマに講演 パリ ギメ国立東洋美術館
日本経済新聞社主催帰朝記念「三浦小平二青磁展」 日本橋三越
- 1991年(58歳)
-
北欧巡回「 伝統工芸名品展 」 招待出品
- 1992年(59歳)
-
《 青磁蓋物 牛車 》 スミソニアン協会サックスギャラリー買上
「 日本の陶芸『今』100選展 」NHK主催 パリ三越エトワール 招待出品
ソウル大学で講演
「 青詩展 」 高島屋(東京 大阪 京都 横浜)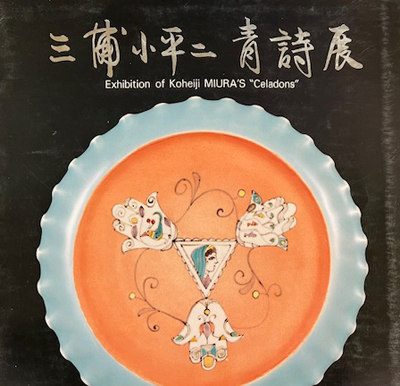
- 1993年(60歳)
-
平成4年度 日本陶磁協会 金賞 受賞 日本伝統工芸展 特持者になる
「 三浦小平二青磁展 」 新潟日報主催 新潟三越「 青磁と私 」をテーマに講演 在仏日本大使館文化広報センター
「 三浦小平二の世界展 」 パリ三越エトワール
《 青磁飾り壺 牧童 》 パリ ギメ国立東洋美術館 収蔵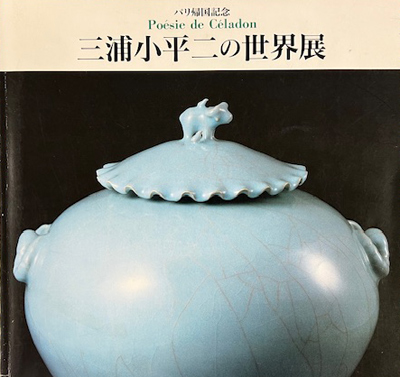
- 1994年(61歳)
-
「 パリ帰国記念 三浦小平二の世界展 」 三越(日本橋 大阪 名古屋 札幌)
M0A美術館 工芸大賞 受賞
新潟日報 文化賞 受賞
《 青磁飾り壺 仔象 》 東京国立近代美術館買上
- 1995年(62歳)
-
「 ジャパニーズ・スタジオ・クラフト展 」 ヴィクトリア&アルバート美術館出品
第42回 日本伝統工芸展 日本工芸会保持者賞 受賞
- 1997年(64歳)
-
第44回 日本伝統工芸展 鑑審査委員
L.A.C国際陶芸アカデミー会員に推薦
- 1998年(65歳)
-
個展(人間国宝認定記念) 日本橋三越
「 人間国宝認定記念 三浦小平二青磁展 」 高島屋(東京 横浜 大阪 京都)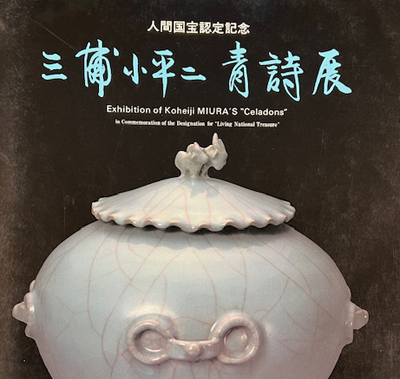
- 1999年(66歳)
-
「 退官記念 三浦小平二展 」 東京藝術大学美術学部美術館主催
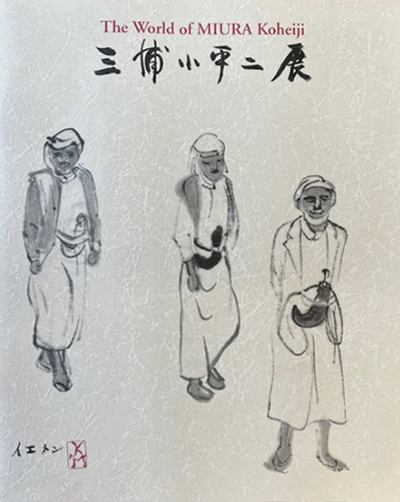
- 2001年(68歳)
-
《 青磁飾り壺 光の杜 》 式年遷宮記念神宮美術館 収蔵
「 六葉会展 」 日本橋三越
- 2002年(69歳)
-
「 伝統工芸と現代陶芸について 」をテーマに講演 佐賀県立有田窯業大学校
「 三浦小平二の知らせざる世界展 」 高萩大心苑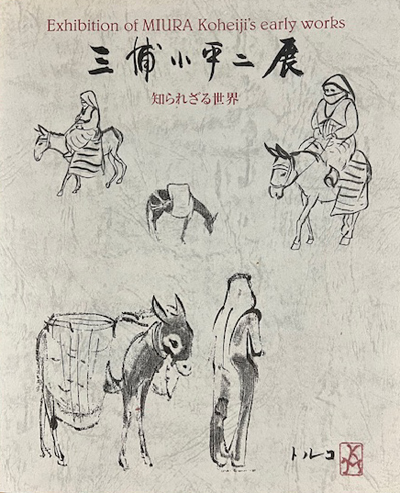
- 2003年(70歳)
-
「 三浦小平二展 青磁の世界 」 くにたち郷土文化館
雪梁舎美術館(設立10周年記念)
- 2004年(71歳)
-
「 佐渡市誕生に寄せて 三浦小平二と小平窯展 」 新潟三越
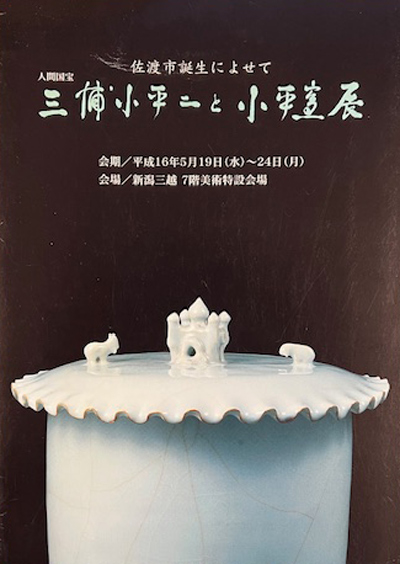
- 2005年(72歳)
-
「 六葉会展 」 日本橋三越
「 人間国宝 陶の美展 」 松屋本店
「 島岡達三・三浦小平二 二人の人間国宝展 」 益子・つかもと記念美術館
- 2006年(73歳)
-
「 制度制定50周年記念 人間国宝展 」NHKなど主催
「 作陶50年 人間国宝 三浦小平二展 」 日本橋三越 新潟三越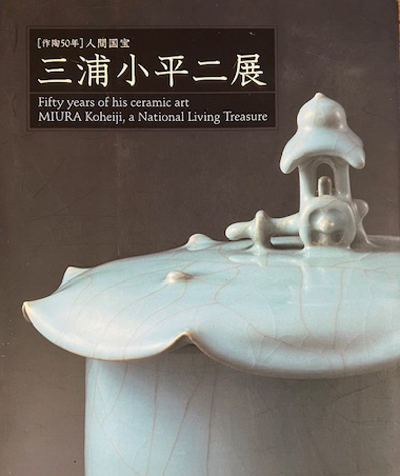
- 2008年
-
「 よく見て 大きく ごしごしと 人間国宝 三浦小平二展 」
くにたち郷土文化館
「 特別展 人間国宝三浦小平二の世界展 」 佐渡博物館 両津郷土博物館
相川郷土博物館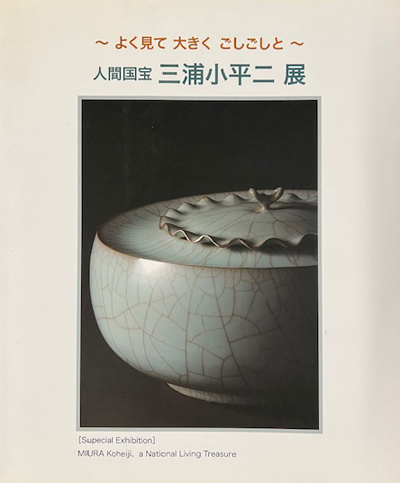
- 2014年 2019年
-
「 ロマンを求めて旅した 三浦小平二展 」 新潟三越
- 2021年
-
「 人間国宝 三浦小平二 旅とともに 」 くにたち郷土文化館
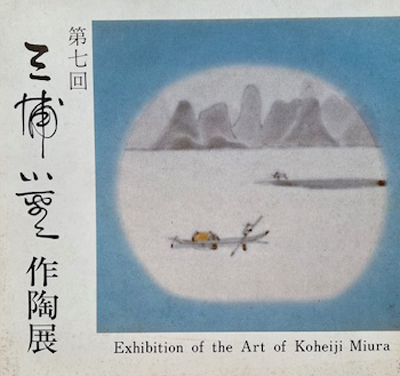
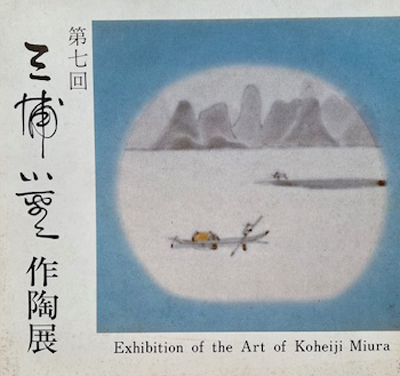
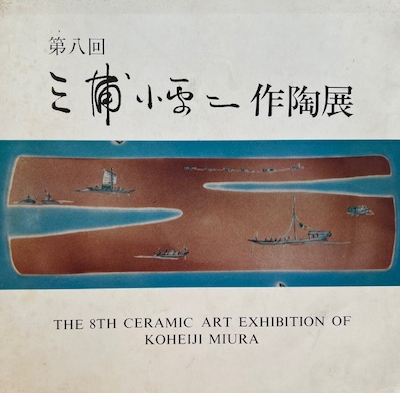
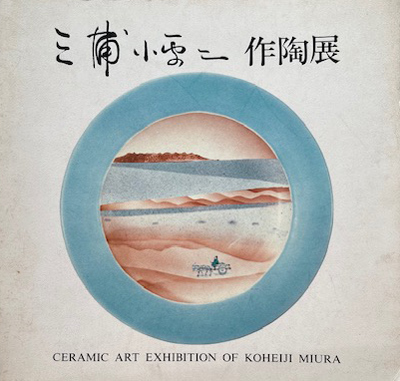
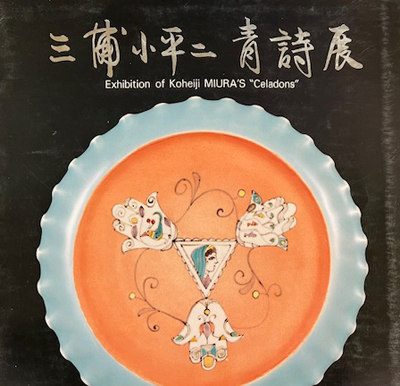
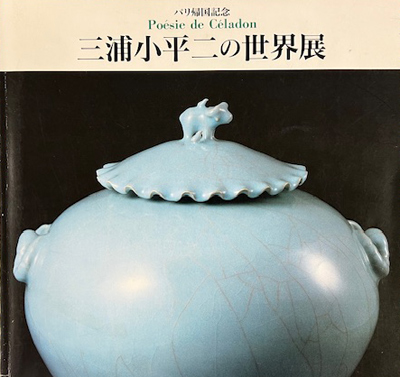
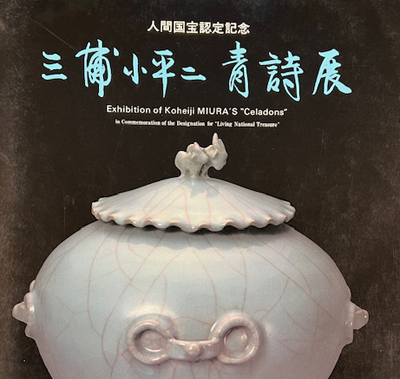
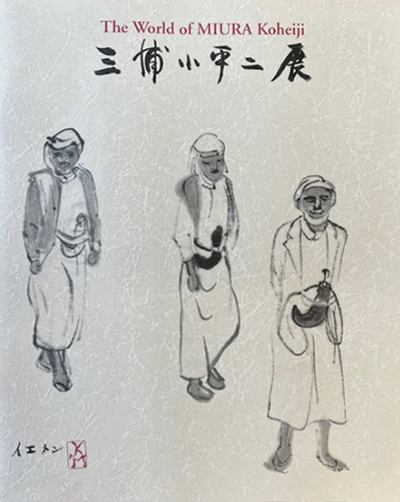
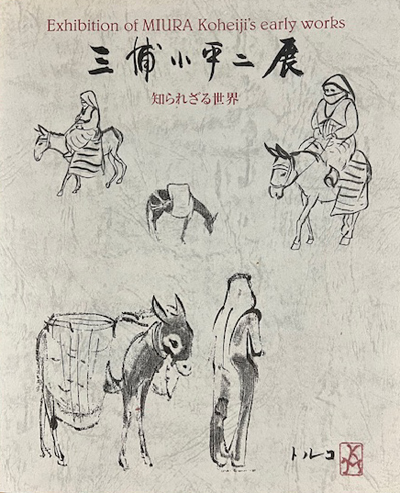
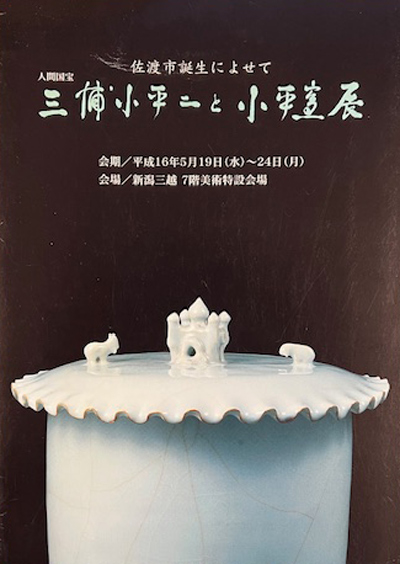
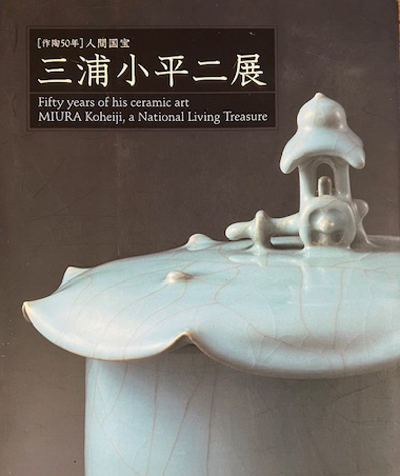
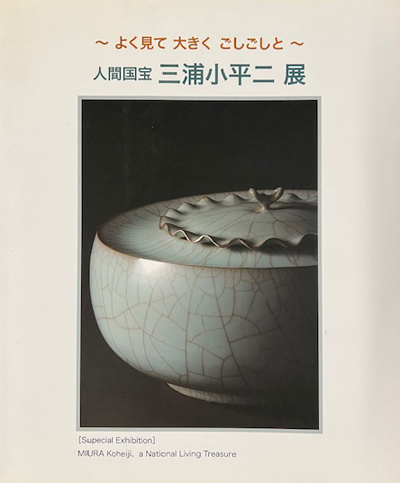
三浦小平二 旅の記録
Journey
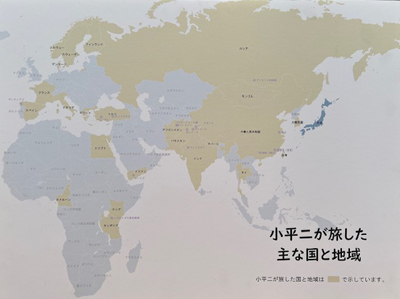
- 1969年
-
中近東 東アフリカへ
- 1972年
-
台湾 故宮博物院へ
(青磁の土が故郷佐渡の土に酷似していることに気付く)
- 1976年
-
アフガニスタン パキスタンへ
(砂漠の中の神秘の湖 バンディー・アミールに出会い、空と水が一体になった大自然を青磁で表現し、その中に人間や動物たちを豆彩で描き、東洋 中近東 アフリカ等の国々の印象を表現する。
青磁と絵画的で彫刻的な表現が調和して三浦小平二のシンフォニーがつくられた。)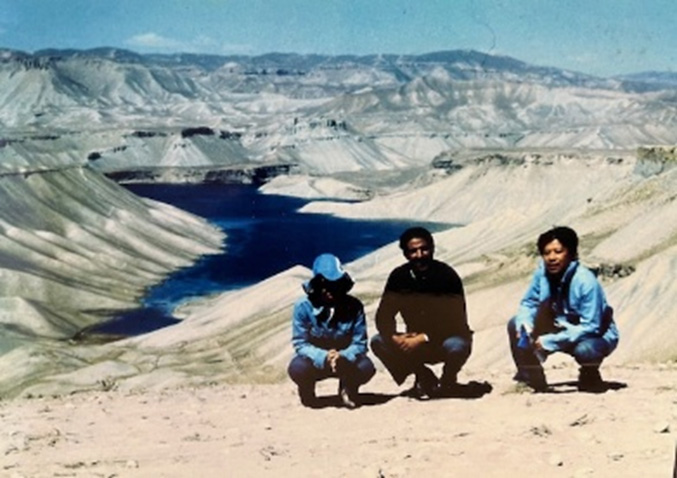 神秘の湖
神秘の湖
パンディー・アミール
- 1978年
-
中国 モンゴルへ
- 1979年
-
華南 華中へ
- 1980年
-
天山北路へ
- 1981年
-
長江へ
- 1982年
-
インド ラジャスタンへ
 インド ラジャスタンにて
インド ラジャスタンにて
- 1983年
-
アメリカへ
- 1984年
-
カシミール ラダックへ
- 1986年
-
トルコへ
 トルコにて
トルコにて
- 1987年
-
イエメン アラブ共和国へ
 イエメン アラブにて
イエメン アラブにて
- 1990年
-
パリ ニューヨークへ
- 1991年
-
中国福建省 客家へ
- 1992年
-
韓国ソウル 西ネパールへ
- 1994年
-
北スペインへ
- 1995年
-
カメルーンへ
- 1996年
-
北欧3国へ
- 2005年
-
ブリアート共和国へ
 ブリアート共和国にて
ブリアート共和国にて
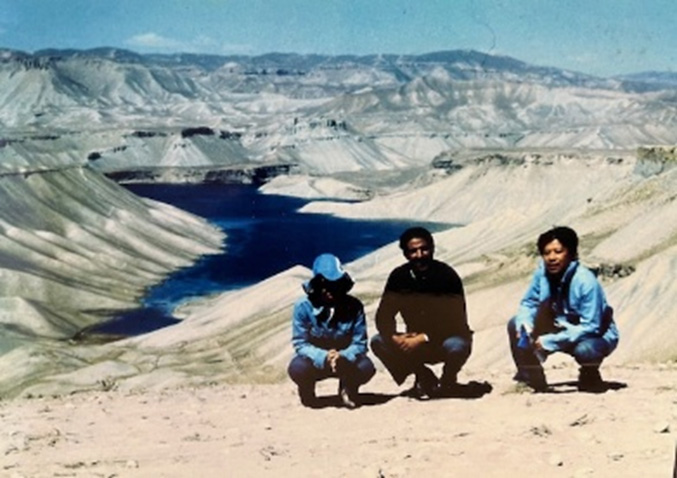
神秘の湖
パンディー・アミール
パンディー・アミール

インド ラジャスタンにて

トルコにて

イエメン アラブにて

ブリアート共和国にて
本HPの写真は 三浦小平二先生のアルバムより使用いたしました。


三浦小平二とむみようい常山小平窯
三浦小平二の芸術の源である「むみようい常山小平窯」
むみようい(無名異)は佐渡鉱山金銀坑中より産出する鉱土(酸化鉄)の一種で 古来中国及び日本に於いて霊薬として用いられていたものです。
初代三浦常山は明治11年この土を使用して軟質だったものを改良し硬質の朱紫泥焼(無名異焼)を創始し3代常山によって佐渡の産業として広く内外に進出した。
初代小平は3代常山の子として父の業を受け継ぎ美術絵画の研究に進み 初代常山の本名であった「小平次」に因み 小平窯を創始し個性的な作風によって活躍しました。
現在 むみょうい常山 小平窯 三浦小平二 小さな美術館として 無名異焼と共に小平二作品を展示 販売しております。